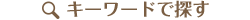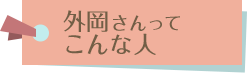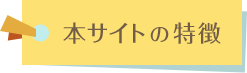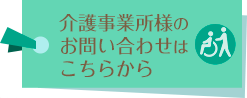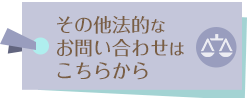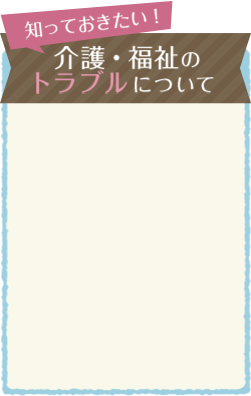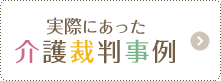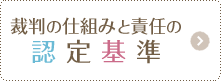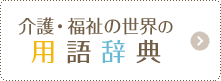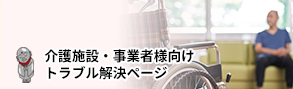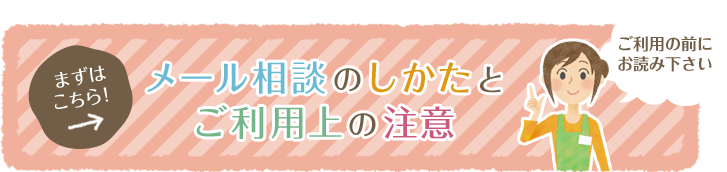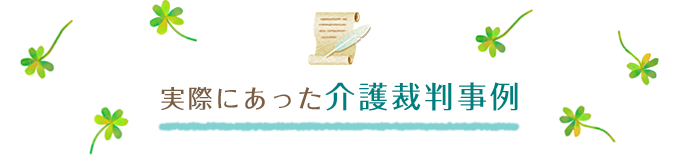
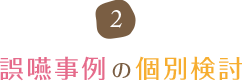
事例番号は前出の表に対応しています。

事例5
- 東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第25683号
- 平成19年5月28日
- 請求額1974万9595円/うち292万6666円を認容。
- 特別養護老人ホームにおける入居者の誤嚥事故につき、介護職員に過失があるとしてその不法行為を認め、老人ホームの開設者の使用者責任が肯定された事例
完全に誤嚥と認められ救命措置が採られるまで、二度容体の急変があったが見守りをするに止めていたという事案です。
(1)利用者の状態
女性 97歳
平成5年に心不全と診断された。平成7年4月、被告施設に入所。。
平成11年に被告施設内で転倒して大腿骨を骨折し、平成12年3月に気管支炎及び肺気腫と診断された。
(2)事故態様
Aは、平成13年8月26日昼ころ、Aの食堂において、出前で取られた玉子丼を食べていた。被告施設では月に一度、昼食に出前を取っており、選択メニューの中から入所者が希望の丼等を選んでいた。Aは事故当時、スプーン等を使用して自ら摂取することが可能であった。この玉子丼には、鳴門巻と呼ばれるかまぼこが細く刻まれた状態で入っていた。
事故当時被告施設では、三名の看護職員が全員休日であった。また非常勤の嘱託医は勤務日ではなく、医療関係者がだれもいない状況であった。
その食事中、Aが口から泡を出していたことに介護職員が気付き、吸引の処置をした(一回目の急変)。
その後、再びAが口から泡を出している様子が発見された。Aは呼吸が苦しそうな様子でみけんの辺りに軽いチアノーゼがみられた(二回目の急変」
このとき、他の入所者が痰を取るために吸引機を使用していたため、介護職員らは、Aの上体を前かがみにして、胃の辺りにこぶしを押し付けたり、背中をたたいたりして、喉に詰まった物を吐かせるようにした。すると、Aは、幾らか噛み砕かれていたものの形が残っていたかまぼこ片一つ(大きさは長さ約二センチメートル、幅約五ミリメートル、厚さ約二ミリメートル程度)を唾液とともに吐き出した。Aは、問いかけに応じるようになり、徐々に顔色が赤みを帯びてきたため、介護職員らは、車いすに乗ったAを食堂から寮母室の前に運んで経過をみることにした。
しかし、介護職員が常時Aのそばに付いて様子を見ていたわけではなく、他の入所者の介助をしながら様子をうかがうという程度であった。
その後、Aが顔面蒼白でぐったりしている様子を介護職員が発見した(三回目の急変)。
(3)事故後の経緯
介護職員らは午後1時5分ころ、一一九番通報をして、救急車の出動を要請した。また、その日はAに嘱託医や看護職員がいずれも不在であったため、嘱託医や看護職員にも連絡をした。そして、介護職員らは、Aを床に仰向けに寝かせ、気道を確保して心臓マッサージを施した。介護職員らが心臓マッサージをしていた際、Aの喉の奥に、かまぼこ片一つ(大きさは長さ約二・五センチメートル、幅約一センチメートル、厚さ約二ミリメートル程度)があることが発見されたため、介護職員はこれを取り出した
その後、嘱託医が到着して対処していたところ、同日午後1時10分ころ、救急車がAに到着した。救急車が到着した時点で、Aは顔面が蒼白で、呼吸及び脈拍が停止しており、意識レベルはJCS300(痛み刺激に全く反応しない状態)であった。気道内は異物が取り除かれていたものの、まだ異物が残っていたため、救急隊員がその異物を更に取り除き、人工呼吸(経鼻エアウエイ)及び心臓マッサージを施したところ、自発呼吸が感じられ、さらに補助呼吸と心臓マッサージを継続し、嘱託医が注射で薬品を投与した。
Aは救急車で国立病院に搬送され入院した。同年7月3日には別病院に転院し、同月9日、同病院で死亡した。
死亡診断書には、直接の死因は老衰であり、直接の死因に影響を及ぼしたと考えられる傷病名は虚血性脳症である旨記載されている。
(4)判決文ハイライト
Aの容態の急変は、Aが玉子丼を食べていた際、かまぼこ片等を誤嚥し、気道が部分的に閉塞されたことにより生じた窒息が原因であると認めるのが相当である。
被告は、平成12年3月にAが国立病院を退院する際、同病院から、食事摂取時にはむせはないか嚥下状態の観察が必要である旨記載された院外看護要約を渡されておりその旨認識していたこと、被告施設には専門的な医療設備はなく、介護職員らは、医師免許や看護士資格を有しておらず、医療に関する専門的な技術や知識を有していないことが認められ、食物を誤嚥したと疑われるような場合に、介護職員らが応急処置として吸引処置を施したとしても、必ずしも気道内の異物が完全に除去されたか否かを的確に判断することは困難であったと考えられること、Aは三回目の急変後、救急隊員が到着した時点で呼吸停止、心停止の状態であって、意識レベルは痛み刺激に全く反応しない状態にあり、入院後も、痛み刺激で動かさなかった手足を少し動かす程度には回復したものの、意識はなく、開眼もしない状態のまま推移したこと、二回目の急変後、Aは意識があり、高度の脳障害にまでは陥っていないことがうかがわれ、一回目ないし二回目の急変時に救急隊員が到着していれば、Aの意識障害の程度を軽減できた可能性が認められないわけではないこと等に徴すると、被告介護職員らは、Aに対し、Aが一回目の急変の際に口から泡を出しており、食物の誤嚥が疑われたため吸引の処置を施した結果、容態が安定したように見えたとしても、引き続きAの状態を観察し、再度容態が急変した場合には、直ちに医療の専門家である嘱託医等に連絡して適切な処置を施すよう求めたり、あるいは一一九番通報をして救急車の出動を直ちに要請すべき義務を負っていたと認めるのが相当である。
しかるに介護職員らは、二回目の急変後も、経過をみるために車いすに乗ったAを食堂から寮母室の前に連れて行ったが、介護職員が常時Aのそばに付いて様子を見ていたわけでなく、他の入所者の介助をしながら様子をうかがうという程度であったのであり、嘱託医等に連絡して適切な処置を施すよう求めたり、あるいは一一九番通報をして救急車の出動を直ちに要請するようなことをしなかった。
そうすると、被告介護職員らは、上記義務に違反した過失により、Aが窒息によって意識レベルを低下させたことにつき不法行為責任を負うというべきである。」
(5)認定損害額の主な内訳
慰謝料400万円 弁護士費用26万円
(6)外岡コメント
Aの直接の死因につき、被告は「容態の急変は、肺気腫による慢性呼吸不全の急性増悪及び肺性心による心不全により生じたものであり、救急隊員の処置によって回復し得るものではなかった。」と主張して因果関係を争いましたが、判決はこれを退け、その一方で「(本件誤嚥は)死亡の直接の原因でないものの、Aがかまぼこ片等を誤嚥したことにより生じた窒息がAの死期に影響を及ぼした面のあることは否定できない」として原告ら遺族の死亡との因果関係の主張までは認められないものとし、「窒息させ意識レベルを低下させた」ことまでについての慰謝料を認定しました。死亡診断書に「直接の死因は老衰であり、これに影響を及ぼしたと考えられる傷病名は虚血性脳症である」とされていた点が重視されたものと思われますが、医学的論争に発展すると認定も極めて困難となる一例であるといえるでしょう。