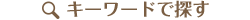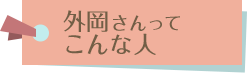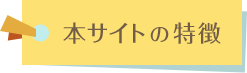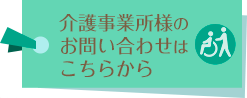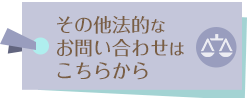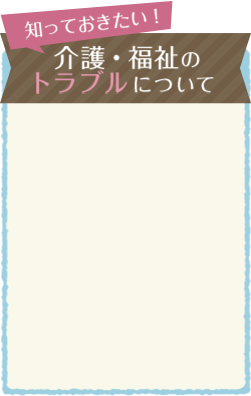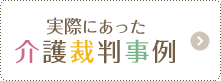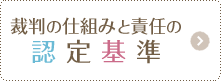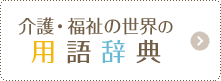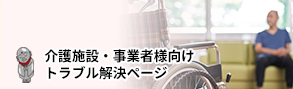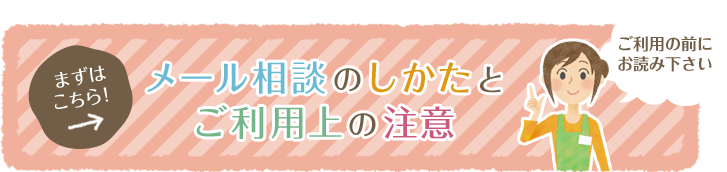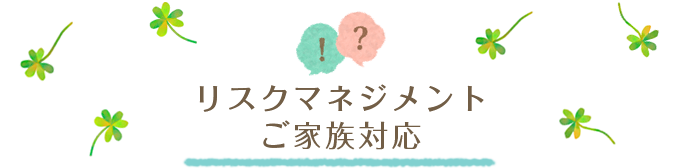
 コロナ関連:感染疑いの認知症入居者を部屋に隔離してよいか
コロナ関連:感染疑いの認知症入居者を部屋に隔離してよいか


住宅型有料老人ホームの施設長です。先日、ご入居者の一人に熱と咳があり、今は収まっているのですが念のためコロナ疑いということでPCR検査を受けて頂きました。
今はその結果待ちなのですが、この方は認知症で徘徊癖があり、他の居室に出入りするといった行動がみられます。この場合、感染拡大防止のため居室に隔離をしても問題ないでしょうか。
身体拘束に当たるためご家族の同意を得たいのですが、このタイミングで連絡が取れません。また、結果的に陰性だった場合、何らかの賠償義務が生じるのでしょうか。

結論から言うと身体拘束(居室への隔離、外部から施錠)して構いません。身体拘束が例外的に認められる要件の中に「本人や家族の同意」は含まれておらず、家族の同意は本来不要です。
身体拘束が「緊急やむを得ない場合」として許される三要件を当てはめてみましょう。
①切迫性:利用者(入居者)本人または他の利用者(入居者)の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
コロナウイルスは高齢者ほど危険性が高いこと、入居者には他に逃げ場がないこと等から、陽性の可能性が1%でもある以上、この要件を満たすといって差し支えないでしょう。
②非代替性:身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
例えば一階フロアには誰もおらず、その一室に移って頂くことが可能といった場合には、そのフロアに限り開放し行動の制約を緩和することが考えられます。しかし、それでも行動の結果フロア全体にウイルスが蔓延する危険性がある等危険回避に繋がらないのであれば、「代替手段」とはいえず結論として居室隔離以外に方法が無いことになります。
③一時性:身体拘束は一時的なものであること
一時性の概念には幅があり、1時間でも1か月でも、要件を満たす場合があります。本件は検査結果が出るまで(陰性であっても念のため2週間は追加で隔離なども可)と期間が限定されており、不相当に長期間ということも無いでしょうから、この要件も満たすものといえます。
重要なことは、居室隔離の前に身体拘束適正化委員会を開き、上記のような三要件に沿った検討を行い、その議事録を「記録」しておくことです。この問題については最後の記録を怠り行政から問題視されるパターンが大半ですので、そこだけは守って下さい。
また、拘束解除についても同様の手順を踏む必要があるので検討と記録をお忘れなく。
最後の質問について、隔離により例えば食事や必要な医療を提供せず、衰弱させたといった事情があれば虐待(ネグレクト)として賠償請求される可能性はありますが、可能な範囲で通常のケアを提供していれば賠償責任を問われることはありません。
この点に関して、確かに拘束の要件ではありませんがご家族との連携は重要です。電話以外にも手紙、メール等の方法で状況や決定事項、経緯等を伝えておくと良いでしょう。他の入居者全員についても同じことが言え、電話以外の通信手段、および第二連絡先を平時から確保できているかチェックしましょう。