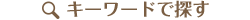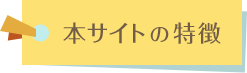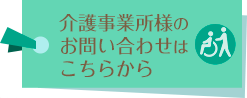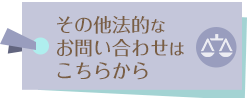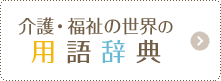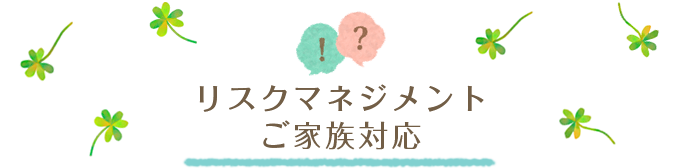
 介護事故を理由に介護職員が提訴されたときの対処法
介護事故を理由に介護職員が提訴されたときの対処法

まさか、介護職の私が訴えられるなんて…
-介護事故を理由に介護職員が提訴されたときの対処法-
介護現場で起きる利用者の転倒・誤嚥等の事故をきっかけに、利用者・家族と施設・事業所との関係が悪化し、裁判になってしまうケースが増えています。
通常、民事上の賠償責任を追及されるのは施設や事業所を運営する法人(社会福祉法人や株式会社など)ですが、稀に現場の介護職員や施設長、ケアマネージャー等の個人が法人と共に提訴されることもあります。
提訴された人は「被告」と呼ばれ、提訴した側である原告(利用者の家族であることが殆どです)の主張に対し反論しなければ自動的に負けてしまうため、嫌が応でも裁判に巻き込まれることになります。
本コラムでは、実際に被告に名を連ねることとなってしまった介護職員の方や、これから自分も提訴されるかもしれないと不安な方向けに、裁判について最低限知っておきたいポイントや対処法を、法律を知らない人でも分かるようやさしくお伝えします。
目次
1-1 民事と刑事
自分が今関わっている状況が、民事なのか刑事なのかをはっきり区別しましょう。
誤解されがちですが、「被告」と「被告人」は全く別ものです。「被告」とは民事訴訟を提起された相手方のことを意味し、一方で罪を犯した容疑で、刑事裁判にかけられた人は「被告人」と呼ばれます。
因みに、マスメディアでよく刑事被告人のことを「被告」と呼びますが、これは誤用であり、被告人と呼称しなければなりません。
民間人が訴訟に関わる場合は、大別して民事と刑事がありますが、民事は通常、お金の支払い(賠償金)を求めて私人が相手方を訴えるものです。一方刑事は、検察官が罪を犯したと考える人を起訴し、裁判官が有罪か無罪か、有罪であればその刑の重さを決めます。
万が一介護職員であるあなたが民事で提訴され「被告」となったとしても慌てる必要はありません。民事上の損害賠償責任については雇用主である法人が加入する損害保険でカバーされ、最終的に原告の請求が認められ賠償命令が出たとしても保険会社が代わりに払ってくれます。
また、裁判では通常弁護士を代理人として立てることになりますが、その弁護士費用等も保険で賄われます(弁護士費用につき万一保険が出ない場合、法人が払うことになります)。
1-2 介護職員が刑事事件に巻き込まれることも…
恐ろしい話ですが、介護職員が現場の介護事故を理由として刑事裁判にかけられることがあります。
長野県の特別養護老人ホームにおいて、入所者の女性に、おやつとして本来ゼリーを配るべきところ誤ってドーナツを配った准看護師が、間食形態の確認義務違反として、業務上過失致死罪で起訴されました。2019年3月25日、長野地裁は求刑通り罰金20万円の有罪判決を言い渡しましたが、その後東京高裁でこの判決は覆され無罪が言い渡され終結しました。この事件は、現場職員に対しあまりに過大な責任を負わせる不当な判決であるとして大きな議論を巻き起こし、記憶にある方も多いことと思います。
その他にも、当然のことですが利用者に暴力を振るい死傷させるような虐待事件は刑事事件となります。また施設職員が、入所者の身体を洗浄する際、シャワーの湯温を十分に確認しないまま高温の湯を浴びせかけた結果、熱傷を負わせ肺炎、敗血症により死亡させたとして有罪判決が出たケースもあります(平成24年4月20日静岡地方裁判所判決)。
このように刑事事件は、お金で解決する民事とは異なり、飽くまで犯罪をしたとされる個人の責任が追及され、有罪となれば懲役などの刑事罰を受ける等大きなペナルティを被るものです。民事と刑事を比べれば、刑事の方が格段に深刻な事態であることは間違いありません。その場合はすぐ弁護士に相談することをお奨めします。
「裁判で全面的に争う等ということは望まない」という方も多いことでしょう。できれば話し合いで穏便に解決したいところですが、残念ながら裁判ではそのような融和路線が通用しないという特徴があります。
刑事では必ず弁護士(弁護人と言います)が付き半ば自動的に言うべきことを言ってくれますが、民事訴訟の場合、原則として自分で対応しなければなりません(但し、介護事故訴訟の場合は弁護士費用等も保険で賄われ、法人の方で探してきた弁護士が職員個人の代理人も兼務することとなるため心配はありません)。そして、訴状に書かれている原告の主張に対し期限までに反論しなければ、自動的に全面敗訴となってしまうのです。
そのため、法人や職員の代理人となった弁護士は、「原告の請求を棄却する」との反論文(「答弁書」といいます)を作成し、相手の言い分を100パーセント否定する主張を展開します。利用者の転倒事故であれば、「自分で転んだ利用者が悪い」と言わんばかりの手厳しい反論をすることもありますが、「自分にも落ち度があった」というような職員個人の真意は往々にして反映されず、法人や保険会社の論理が優先されるということが起こります。
なお、地方裁判所で行われる訴訟はこのように「勝つか負けるか」という争いになりますが、その手前の話し合いの場として簡易裁判所で開催される「調停」というものもあります。これには強制力はないため望まない場合は応じる必要もないのですが、裁判所で第三者的立場にある調停員を間に挟み、お互いの潰し合いではなく話し合いでの解決を目指す手続であり、一方で「和解のテーブルについた以上必ず譲歩し合意しなければならない」といった義務も無いため、申し立てられた場合は積極的に応じることを検討されるのが良いものと考えます。
裁判官は神様ではないので、問題とされる介護事故が起こる瞬間にタイムワープして現場を目撃する、等ということはできません。ではどのようにして原告・被告の言い分のどちらが正しいかを見極めるかというと、それは双方の提出する「証拠」から認定しています。証拠とは、私達が普段使う言葉と同じ意味で、ある事実が真実であることを示すあらゆるものが証拠となります。
その代表的なものは事故報告書や介護日誌、ケアプラン等の書面記録ですが、関係者の会話を録音した音声記録、映像、杖や車椅子の現物等も証拠になり得ます。
その意味で、介護現場において日常的に付ける記録は極めて重要です。職員個人が知覚し経験したことはできる限り詳しく、ありのままに記録し、後から見返して齟齬・矛盾が無いように注意しましょう。
正しい記録の付け方についてはまた別コラムで解説しますが、ポイントとなる心構えは「自分達に有利となるか、不利かといったことは一切考えず、主観を交えずありのままに正確に記録する」ということです。例えば認知症の利用者が、「待っていて下さいね」という職員の指示に従わず、無言のまま立ち上がろうとして椅子から転落した事故が起きたとします。そのとき、利用者は、本当は職員の呼びかけを理解せず何も言わず立ち上がったのに、「利用者が理解していたというストーリーにするために、「分かったよ」と返答したことにしておこう」等と画策しそのように報告書に書いてしまうと、そこに小さな嘘が紛れ込むことになります。これは違法行為であり許されません。
人間は弱い生き物ですから、やはり自分に危害が及ぶ危険性があるとなると保身に走ってしまいがちです。「もし自分たちに不利となるような事実を記録すれば、裁判で負けて多額の賠償金を負わされてしまうかもしれない」等と想像すると、極力そのような事実は省こうと考えてしまうかもしれません。
ですが、民事訴訟というものは、言ってしまえば所詮お金で解決するものでしかないところ、繰り返しになりますがその金銭的負担は損害保険でカバーされます(ただし、保険会社と契約する上限額を超える場合は例外です)。
介護職員も同様に法人の加入する保険で対応される以上、自分まで訴えられたからといって「もう自分の人生はおしまいだ」等と深刻に受け止める必要はありません。裁判のリスクを気にし過ぎ、目の前の利用者と真摯に向き合えなくなるのでは本末転倒です。日々の記録も第三者的観点から客観的かつ冷静に書くようにしたいものです。
4-1 訴状の郵送
民事訴訟は被告とする相手方の住所地に訴状(被告に対する請求とその理由を記載した書面)を郵送することから始まります。訴状には、「被告法人及び被告〇〇(介護職員の氏名)は、原告に対し金○○万円を払え」等と物騒なことが書かれています。訴えられた側は、裁判所にそのような賠償命令を出させないようこれに対し必死に反論し、原告・被告間で言い分をぶつけ合うことになります。
介護職員を提訴しようと考えた場合、利用者側としてはその職員の氏名は分かっていても個人的な住所までは普通知らないので、その職員が所属している施設・事業所の所在地に訴状を郵送することになります。通常は施設運営法人と連名で訴えられるため、施設長など上の立場の人から「実は今回、あなたも被告にされている」と初めて知らされ、驚くという流れになるでしょう。逆に言えば、既にその施設・事業所を辞めているのであれば、その施設事業所で起きた事故を理由として起こされる裁判の被告にされることは(現実的に考えて)無い、と言えます。
4-2 口頭弁論
「裁判」と聞くと、ドラマや小説のように法廷で弁護士が丁々発止の弁論を繰り広げる…といったイメージが浮かぶかもしれませんが、現実の裁判はそのようなことはなく、大変地味なものです。裁判のクライマックスで開催される「証人尋問」には確かにドラマのような華やかさがあるかもしれませんが、日本の民事裁判の法廷にはアメリカの陪審員のような「ギャラリー」が居らず、テクニックを駆使して陪審員にアピールするといった面が無いため、その意味ではやはり地味といえます。
民事訴訟は通常、毎月1回の頻度で口頭弁論期日が開催され、そこで原告、被告の双方が法廷に現れるのですが、やることは事前に提出した書面(準備書面といいます)を「読み上げますか」と裁判官に促され、「はい」と答えるだけ。裁判官は「では次の期日は○月○日とします。被告は一週間前までに主張書面を提出してください」等と指示し、それで終わりです。 これは、「口頭弁論」と言いつつも実際には書面が重視されるという、民事訴訟のルールによるものです。従って大抵一回の裁判期日はものの数分で終わってしまい、また1ヶ月後に向けて相手への反論を準備する(或いは相手からの反論を待つ)という、知らない人からすれば悠長に思われる様なペースで進んでいくことになります。
「もし自分が訴えられたら、毎回仕事を休んで裁判所に行かなければならないのか」と不安な方もいるかもしれませんが、その心配は要りません。あなたの代理人となった弁護士が、裁判期日への出頭や準備書面の作成等を、代わりに全て対応してくれます。通常は法人が主たる被告として反論等を組織全体として構成していきますので、職員個人が意見を求められ、自分で主張を考えなければならないということはまず無いものと考えて良いでしょう(裏を返せば、言いたいことがあっても基本的に採用されないということなのですが)。
一方で、民事訴訟の争点とされている事故について自身で見聞きした事等については詳しく弁護士からヒアリングされます。基本的には自分の記憶に従い覚えているままに話せば良いのですが、別の職員が作った事故報告書等と矛盾する点があったりするとそこを整合させるために認識を改めなければならないことも出てくるかもしれません。
後述するように職員個人が提訴される理由はいくつか考えられ、ケースバイケースにはなるのですが、事故の核心となる事柄については非常に細かく、何度も尋ねられることになると覚悟しておいたほうが良いでしょう。そのようなときに困らないよう、備忘録を付けておくのも良いかと思います。
4-3 和解
裁判期日が複数回重ねられ、1、2年が経過する頃には大抵お互いの主張や立証(証拠を提出し自分の主張が正しいことを証明すること)も出揃い、裁判官がそのときの心証に基づき、原告被告の双方に対し和解を奨めることがよくあります。ここで被告として和解に応じ、例えば「100万円を原告に支払う」と約束した場合、これを払うのは結局保険会社ということになります。金銭的負担のない法人や介護職員としては早く和解を成立させ終わらせたいと思うことも多いのですが、保険会社としては「根拠のない訴訟なので最後まで争うべき」と主張するなど、施設側と保険会社との間で思惑が一致しないこともあります。
4-4 尋問
和解が不成立に終わると、いよいよ裁判のクライマックスである「尋問」(当事者尋問や証人尋問)が開催されます。これは、原告である利用者家族や、提訴された介護職員本人、或いは当事者以外の関係者が証人として裁判所に集められ、裁判官の目の前に座り原告・被告双方の代理人弁護士から質問を受け一問一答で答えていくという手続です。
尋問を受ける立場としては非常に心理的負荷が大きく、事前の準備やリハーサルも含め多大な時間と労力を費やすところ、当事者の間には「できれば尋問前に和解してしまいたい」という思惑が働きます。これを見越して裁判官は、尋問に入る前に一度は和解を奨めるのです。
尋問を終えた後も和解の勧試がなされることもありますが、それでも成立しないときはいよいよ裁判官が判決文を書くことになります。これまで当事者が重ねてきた主張・立証を総合的に評価し、原告の言い分が正しいと思えば被告に対し賠償命令を、そうでなければ原告の請求を認めない(棄却する、といいます)旨の判決文を書きます。判決までいく場合は、提訴から2,3年が経っていたということもざらにあります。
4-5 賠償額の支払い
最終的に保険会社が賠償額を支払う点は、和解のときと同じであり、もし民事訴訟で敗訴しても介護職員が個人的に金銭的負担をしなければならないということはまず考えられないことですので、その点はご安心ください。一方、保険に加入する法人としては、翌年以降の保険料が上がってしまうといった不利益が生じます。
4-6 審理のやり直し
地裁の判決に納得いかない場合は、さらに上級の裁判所(高等裁判所)に対し審理のやり直しを求めることができます。これを控訴と言いますが、控訴で行われる手続きは通常、地裁で延々と積み上げられた主張立証をベースに別の裁判官が見直すというだけのことですので、一回目の口頭弁論が開催されれば次は判決言い渡し、という様にすぐに終わってしまいます。
介護事故の訴訟は長引きやすく、判決もまちまちであるため控訴もされやすいと言えますが、大雑把なイメージとしては控訴審というものは飽くまでおまけであり、第一審である地方裁判所での裁判がメインなのだと認識されると良いでしょう。
民事訴訟を起こす権利は憲法上の人権であり、事実上どのような理由、根拠であっても裁判所に訴状を提出することは可能です(その後、裁判所の方で正式に受理するか否かはまた別の問題ですが)。
「お互いに裁判をしない」との合意を当事者間で取り交わすことは論理上可能ではありますが、介護サービスの利用契約書にそのような文言を書くことは通常考えられません。まして施設・事業所に勤務する一職員の立場では、「こうすれば絶対に利用者やその家族から提訴されることはない」という確証を得るための方法がありません。
そうなると、極論「訴えられるか否かは運次第」ということになってしまうのですが、これは介護の仕事に限られるというものでもなく、他のあらゆる民間事業でも条件は同じです(飲食店で熱い飲み物を顧客にかけてしまい、やけどをさせてしまった場合等)。
また、仕事以外でも例えば車を運転中に交通事故を起こせば、被害弁償を求めて被害者から民事訴訟を提起される可能性もあるのであって、その意味では私達はそもそも法治国家で暮らす以上「裁判沙汰」と無縁でいられるものではない、とも言えるでしょう。
もっとも、介護現場では高齢の利用者が転倒等の事故を起こしやすく、また一度転ぶとその衝撃で大腿骨骨折等の重大な怪我に繋がりやすいという特徴があり、現場で利用者を見守り支える立場としては気が気ではない、ということもあろうかと思います。
何故利用者側は法人だけでなく、介護職員まで訴えるのでしょうか。その職員個人が虐待をした等、個人としての責任が重いからという場合もあるでしょう。ですが、偶然起きた事故と言い得る転倒事故であってもその場に居た職員が提訴されることがあるのは、「真実を明らかにするため」という明確な理由があるのです。
事故が起きれば事故報告書を始め詳細な記録が付けられるため、書類の記録としては十分かもしれません。ところが、そうした記録と事故直後の職員の説明との間に矛盾が見つかると、利用者家族としては「どちらが真実なのか、裁判をしてでも明らかにしたい」と考えるようになります。しかし前述のように、民事訴訟というものは1ヶ月おきに主張の応酬をずるずると続け、判決までは1、2年かかってしまうこともざらにあります。
お互いの主張や立証(証拠を提出し自分の主張が正しいことを証明すること)を一通り終え、いよいよ証人尋問で職員の証言を聞こうという段になったときには、その職員は既に辞めてしまっているかもしれません。そうなると利用者側としては真実が闇に消えてしまうため、「ならば最初から被告として、逃げられないようにしておこう」と考えるのです。
冷酷な話かもしれませんが、職員の立場からすれば施設・事業所をいつでも辞めることができ(法的には最低限2週間前の退職届けが必要)、個人情報保護法の壁で住所等の個人情報は明かされない以上、致し方ないことなのかもしれません。
以上、民事裁判について最低限知っておきたいポイントと対処法を解説しました。頭では分かっていても、実際に自分が訴えられるということはショックであり、裁判が終わるまでの間ずっと気が重いものです。ですが、介護現場の事故が裁判沙汰にまで拗れてしまうのは理由があり、不毛な裁判を回避する方法、現場で意識的に取り組むべき明確な予防策が存在します。事故自体をゼロにすることは不可能かもしれませんが、だからこそ事故をトラブルにさせない方法を取り入れて頂きたいと思います。 詳しくは介護トラブル解決ページをご参照ください。